

\安心の「研修動画+資料」事後送付保証つき/
7~9月中のリアルタイムでの受講が難しい場合でも、本講座にお申込み頂ければ、
お申込み頂いた回の研修動画と資料を後日メール等で送付致します!
視聴期間は2025年11月30日(日)まで
ユニバーサル化時代に
賢明に対処できる大学を!
大学の意思決定・計画策定支援のための
情報収集・分析スキルが
体系的・計画的にマスターできる講座!
延べ150人以上の
国公私立大学関係者が受講し
大好評!
大学IRプロフェッショナル
養成講座とは?
~私学助成の配点区分に配慮した
「修了証書・発行プログラム」~
毎年好評を博している本講座は、今まで延べ150人以上の国公私立大学関係者の方々に受講いただき、今年で5年目を迎えます。
大学IR(Institutional Research)は、データに基づいた教育改善を推進するツールとして、主に米国の取り組みが紹介され、我が国でも導入が進んできました。
近年では、教育のみならず、研究活動・人事・財務・施設設備など、多岐に関わる分野でのIRが期待されています。
例えば、令和2年1月の「教学マネジメント指針」では、「教学IR体制の確立」や「教学IRに関わる専門スタッフの育成」が各大学に要請され、それに続く令和3年2月の「教育と研究を両輪とする高等教育の在り方について(審議まとめ)」では、「大学運営IR体制の構築」や「大学運営IR人材の養成」が各大学に求められています。
さらに、これからの大学IRには、大学の運営および経営の改善のために必要なデータの確保、情報処理、分析、報告技術などのスキルだけでなく、組織の中でIRの効果を発揮するためのマネジメント技能も必要です。
本講座では、大学IRの業務に携わる全ての方を対象に、こうしたスキルや技能を習得し、ユニバーサル化時代にあって、経営分野や教学分野の大学改革を情報収集・分析面から支える「大学IRプロフェッショナル」を養成します。
※なお、本講座では、私学助成の配点区分に配慮し、所定の課程を修了された方に「大学IRプロフェッショナル養成講座 修了証」を交付しております。「修了証」の交付をご希望の方は、お申込みフォームで、「修了証交付を希望」をお選びください。
近年わが国の大学に強く求められている「経営IR」と「教学IR」の「基礎知識、応用力、実践」の
主要なスキルを“ 体系的” にマスターすることができます!
大学IRの最新テーマを取り上げ、大学IRの「知識が増える」だけでなく、講座で習得したことが「“すぐ” 実践できる」ところまで、
しっかりとサポートします!
高等教育改革政策で“いま”全大学に育成することが要請されている「大学IRプロフェッショナル」へと
確実に成長することができる本格的な講座です!
大学IRプロフェッショナル養成講座の5大特長
Strong Point

IRで必要となる
統計学やデータ処理技術を
無理なく学べる!
大学IRの業務に携わる方が、無理なく、IRで必要となる統計手法やSQL、R、Excel、Accessなどのデータ処理技術を習得していただけるよう、基本レベルからスタートし、実践例の紹介やワークを行うなど、平易かつ徹底的に説明します。
Strong Point
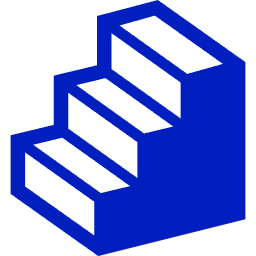
学修成果の可視化や教学IR手法を
3つのレベルに分けて
わかりやすく講習!
各大学でお悩みの多い学修成果の可視化の方法や教学IRにおける問いの立て方について、3つのレベルに即した個人ワークや分析事例の紹介を行い、その方法をしっかりと身につけることができます。
Strong Point
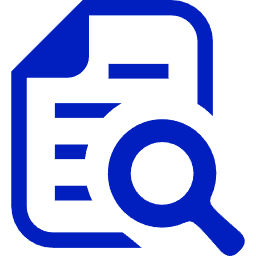
大学IRの業務に
直結した実践事例を
幅広く紹介!
大学経営、奨学金、卒業生調査、エンロールメント・マネジメント、研究活動のモニタリングなど、大学の業務に直結する具体的な実践事例を幅広く取り上げ、大学の業務に役立つ内容を丁寧かつ実務的に解説します。
Strong Point
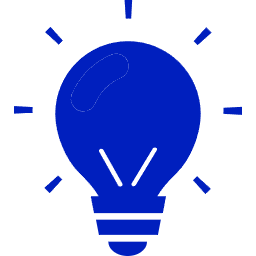
先進的な大学IRの取組みを学べる
貴重な機会!
九州工業大学の取り組みを参考に、ゼロからIRシステムを構築する方法や、東京科学大学におけるIRとDXの推進方法をお伝えするなど、先進的な大学IRの取組みを学ぶことができる貴重な機会を提供します。
Strong Point

大学IRの現役実務の
エキスパート講師陣!
5名の講師陣は、各大学の現場でのIRをはじめ、関連する改革事業を展開しているプロフェッショナルです。また、講師陣は、他大学のIRも多面的に支援しています。それぞれの専門分野を活かした質の高い最先端の講座を展開します。
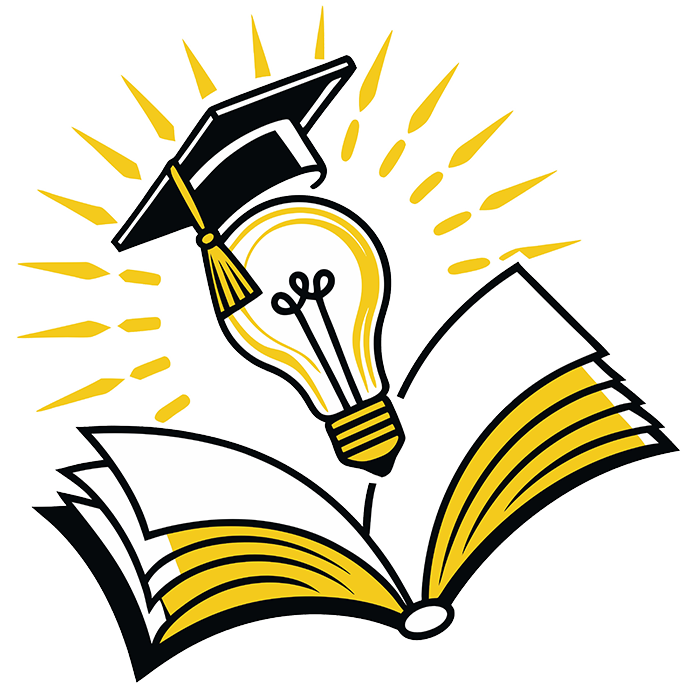
このような方はぜひご参加ください
- IR部門の新任担当者の方など、大学IRを初めて学ばれる方
- 大学IRを学ばれたことのある方で、IR部門の新任の管理職の方
- 大学におけるIR実務者や大学IRに関心を持つ方
- 大学IRをこの機会にリスキリング(学び直し)したいとお考えの方
- 大学IRを活用した意思決定に携わる大学経営幹部の方
- エンロール・マネジメントに携わる大学教職員の方
- 大学の戦略的経営を立案する立場にある大学管理運営職の方
- IR室等に所属し、教学IRの業務を担う大学教員・職員の方
- 大学評価室に所属する質保証担当の方
- 学修成果・教育成果の把握・可視化に取り組む大学教員・職員の方
- 中退率の把握や中退防止施策を立案する立場にある大学教員・職員の方
- 統計分析に関心がある高等教育研究分野の研究者
- IRとDXの関係について関心がある大学関係者の方
- 大学IRの知識が必要なコンサルタントの方
- インスティテューショナル・リサーチャーになることを目指す方 など
\1講座のみの受講可能!/
プログラム
(全8日/全日 13:30~16:40)
各大学で大学IRを進める上で、「IRとは何か、IRはなぜ必要か、IRに必要なスキルとは、IR組織とはどのようなものか」などといった「大学IRの本質」を理解することが大切です。
また、各大学のIR担当者には、統計理論や統計処理の基礎的な知識・スキルを身につけておくことが最低限求められます。
そこで、第1回講座では、日本IR協会の森会長が全8回講座に通底する「大学IRの本質」とIR業務で必要となる「統計理論の基礎」について、わかりやすく解説します。また、データ分析に精通している田中講師がExcelを使った統計処理の基礎をやさしく説明します。
第1章では、IRの概要・背景、IRに必要なスキル・人材、IR組織の設立・運営の方法について、実践的な知識を学びます。
第2章では、IRで必要となる「統計の基礎的な事項」や「Excelを使った記述統計の処理」について初歩を実習します。
第3章では、田中講師が提供するExcelデータをもとに演習を行い、初心者の方でも、表やグラフ(度数分布表、ヒストグラム、箱ひげ図)を作成できるようになることを目指します。
第1章 IRの概要・背景と必要なスキル・人材
[担当講師:森 雅生 先生]
- IRの歴史と背景、概要
- 必要なスキルと人材および組織
- 教学マネジメント指針とIR
第2章 統計(理論)
[担当講師:森 雅生 先生]
- 統計の重要性(データに基づく意思決定、分布・記述統計と推定統計)
- 一変量(ヒストグラム、平均値、標準偏差、四分位数、正規分布、変動係数・散らばり比較、歪度)
- 一変量の練習問題
- 多変量(相関関係、予測、要約、分類、推定統計の必要性について)
- グラフの活用とデータの可視化(散布図、バブルチャート、箱ひげ図)
- 参考文献の紹介
第3章 統計(実践)
[担当講師:田中 要江 先生]
- 今回作成する表・グラフの紹介
- 度数分布表(表の概要と作成方法、セルを参照している数式の貼付け方法、階級の作り方、実践)
- ヒストグラム(ヒストグラムの作成方法、書式設定、実践)
- 箱ひげ図(箱ひげ図の見方と作成方法、書式設定、ユーザー設定リストの登録・使用方法、実践)
- ExcelにCSVファイルを取込む方法の紹介
大学IRを効率的に遂行するために、データウェアハウス(DW)などのシステムを導入して、学内のデータの収集・分析を行う大学が増加し、DWへの関心が近年高まっています。
また、IRデータの分析にあたって、多くの大学でAccessのソフトウェアが使用されていることから、IR担当者には、Accessの機能を使いこなすスキルが求められています。
さらに、昨今、わが国の大学の「研究力の低下、経営状況の悪化、DXの遅れ」などが問題視される中で、「研究IR」、「経営IR」、「IRとDX」といったテーマに注目が集まっています。
そこで、第2回講座では、DWを中心としたデータ処理の理論を説明した上で、Accessを使ったデータ処理の演習を行い、大学IRの最新・重要なテーマについて理解を深めます。
※なお、第5章の講義は、Accessが使える環境にあるけれども、Accessを使ったことがない方々を対象としております。そのため、ご受講時は、Accessが使用できるPCをご自身でご用意ください。
ただし、第3章の講義でExcelを使って行ったことをAccessで行うことも可能となる方法を紹介しますので、AccessがインストールされていないPCをお持ちの方でも、第5章の講義内容についていけるプログラム構成になっております。
第4章では、IRの役割とDWの概要や構築に関する理論を「誰でも理解できる」ように平易に説明します。
第5章では、IR業務で使う範囲のAccessの機能を理解した上で、Accessを用いてテーブルを結合し、クロス集計による分析手法を紹介します。そして、田中講師が提供するExcelデータをもとに演習を行い、初心者でもAccessを使ったデータ結合や、Accessで整形したデータを用いたクロス集計ができるようになることを目指します。
第6章では、昨今、各大学のIR業務において重要性が増している「研究IR」、「大学経営へのIR活用」、「DXとIRとの関連」といったホットなテーマについても取り上げて、わかりやすく解説します。
第4章 データ処理(理論)
[担当講師:森 雅生 先生]
- IRの役割とデータウェアハウス(DW)の目的
- DWが備えるべき特性(サブジェクト指向性、統合性、時系列性、不変性)
- DWの構成要素
- ER図(Entity Relationship Diagram)とは
- 組織におけるIR情報流通のために(オントロジーログ(olog)、BPM)
- データベースからデータウェアハウスへ
- BPMとデータウェアハウス
- DXとIRについて
第5章 データ処理(実践)
[担当講師:田中 要江 先生]
- Accessの基礎(IR業務を想定したAccessの使い道、オブジェクトの概念・紹介、ファイルのインポート)
- クエリ操作に入る、その前に(データベースの基礎知識、データの格納方法、主キーと外部キー)
- クエリ操作:単数テーブル編(クエリデザインの使い方、実践)
- クエリ操作:複数テーブル編(テーブル結合の方法、クエリの名前の保存、データのエクスポート、実践)
- クロス集計(ピボットテーブルの使い方、実践)
- 「閉じるときに最適化する」の設定
- SQLの紹介
第6章 研究IR、経営IR、DXとIR
[担当講師:森 雅生 先生]
- 研究IR
- 引用とは
- 基本的なビブリオメトリクス(被引用数、被引用インパクト、インパクトファクター、ベースライン、引用の傾向)
- 引用の順位づけから導かれる指標(パーセンタイル、Top n % 論文、h-index)
- 論文の引用数に関する指標のポイント
- 大学経営、IR、DX
- 大学経営へのIRの活用(経営支援を行うIR)
- 教育コストの測定(CVP(cost-volume-profit)分析、包絡分析法)
- 教育コストの測定の練習問題
- リサーチクエスチョンの立て方
- 課題に対する解の提示参考文献の紹介
- まとめ
“いま”大きな注目を集めている「知の総和」答申をはじめとした近年の高等教育政策において、教育情報データベースを活用して、教育の質を評価し、その情報を公開する取組みを行うことが各大学に対して強く求められるようになってきています。
そこで、第3回講座では、教育データの扱い方について、「教育データ」と「SQL」という2つの章に分けて、初歩からやさしく丁寧に講義を行います。
SQLを使ったことがない方でも、安心して参加できる内容となっていますので、どうぞお気軽にご参加ください。
第1章では、教育データにはどのようなものがあるかをやさしく具体的に説明します。多くの大学で悩みを抱えている「中退予防」に関する内容を取り上げて、教育データの周辺事項を講習します。
第2章では、教育データの把握、抽出、可視化に関する技能としてSQLを取り上げて、わかりやすく解説します。
講師がSQLのデモ環境構築の仕方を案内し、SQLにはじめて触れる方でも、無理なくSQLの技能を身につけていただけるよう、実演付きでSQLの操作方法を紹介します。
第1章 教育データ
- 教育データにはどんなものがありますか?
- 使用できる教育データ・利用できる教育データ
第2章 SQL
- 正規化
- データ抽出
中教審答申や第4期機関別認証評価において、「教育データの可視化」、「内部質保証の実質化」、「教学IRシステムの構築」が各大学に強く要請されるようになってきています。
そこで、第4回講座では、IRシステム構築、可視化分析という観点から、教育データの扱い方について、ゼロからわかりやすく解説します。
本講座の「翌日」から“すぐに”実践できることを目標とします。
第3章では、九州工業大学の取り組みを参考に、ゼロから「IRシステム」を構築する事例を紹介します。
第4章では、「教育データの可視化」分析の概要を説明し、「内部質保証」の観点からの効果的なデータの見せ方について、具体的な例を用いて、解説します。
第5章では、第2章のSQLによるデータ抽出に関する技能の統計解析ソフトRでの実現方法を取り上げて、初歩から丁寧に解説します。
講師がRのデモ環境構築の仕方を案内し、Rにはじめて触れる方でも、無理なくRの技能を身につけていただけるよう、実演付きでRの操作方法を紹介します。
第3章 IRシステムの構築
- 九州工業大学の事例
- 必要な機能と実現方法
第4章 教育データの可視化
- グラフの種類
- 効果的なデータの見せ方
第5章 Rを用いた可視化
- SQLとの比較
- グラフ表示
大学IRは、わが国の大学の間で普及してきましたが、「IR室を設置してはみたものの、あまり実質的に機能していない」といった声をよく耳にします。この原因として、十分なデータが集まらず、説得力のある分析ができないために現場で活かせないという点が指摘できます。
DXの重要な取り組みの1つはデータ利活用の促進であり、IRはデータ利活用の代表的な活動です。この意味でIRとDXは密接な関係にありますが、このような観点に立って両者が連携するような取り組みは多くありません。
そこで、第5回講座では、IRとDXの関係についての知識を提供します。東京科学大学で大学DXを推進する今井先生が、その豊富な知見と経験に基づき、受講者の方々からのご質問を随時お聞きしながら、徹底的にわかりやすく講義を展開します。
第1章では、IRが進まない理由やIRを進める際の重要なポイントについて、東京科学大学の事例を紹介しながら説明します。
第2章では、DXの意味や狙いを概観し、大学に適用する場合に注目すべき点やIRとの関係について解説します。
第3章では、DXの有効な手法である「ビジネス・プロセス・マネジメント(BPM)」の基本的な考え方を紹介します。BPMに基づくプロセスの可視化の有効性に着目し、有用なプロセス可視化ツールとしてRanabaseをご紹介します。
「大学組織のDX」や「IRとDXの関係」を本格的に学べるのは、ビズアップ総研の講座だけです。
第1章 IRを進める際のポイント
- 何故IRが進まないのか意見交換
- IRで使うデータをデータマネジメントの観点から分類
- データの起点から終点までの概観
第2章 IRを活用した大学DXとは
- 日本におけるDXの定義と狙い
- DXを大学に適用する際に踏まえるべきポイント
- IRとDXの融合
第3章 大学DXを実践するために必要な知識
- ビジネス・プロセス・マネジメント(BPM)の紹介
- プロセスを「可視化」することの意義
- 業務を分析すると見えてくるもの
BPMはDXに限らず、大学業務の見直しや効率化に有効ですが、いざ実践しようとすると様々な苦労に直面します。さらにIRにとっても有用な業務プロセスを構築しようとするとデータの発生から活用まで俯瞰する必要があり、より一層難しいものとなります。
そこで、第6回講義では、BPMに基づく業務プロセスの分析を簡単な実践例を取り上げ、プロセスにともなってどういうデータが生成され、変化していくのかを体験していただきます。さらに、プロジェクトマネジメントの基本を概観したうえで、業務改善の実例を紹介します。
第4章では、業務プロセスを可視化する方法を簡単に紹介し、プロセス図の読み方を修得します。同時に、プロセスの中でデータがどのように発生し、変化していくかを概観します。IRではプロセスそのものよりもデータが重要になりますが、DXとしてはプロセスの改善が肝になります。
第5章では、講師の経験に基づく事例を交えながらプロセス改善プロジェクトの進め方を紹介します。実際の現場ではどのようなことが課題になるのか、それをどう乗り越えるのかという実践的な内容になります。
IRを前提としながらDXを進める実践的な知識を身につけることができます。
第4章 業務分析の演習
- Ranabaseをつかった業務プロセスの記法
- 現状プロセス(as-is)と改善プロセス(to-be)
- 業務プロセスとデータについて考察
第5章 プロセス改善プロジェクト
- 改善プロセスとデジタルツールをセットで行うDX
- プロセス改善プロジェクトのポイント
- 事例紹介
近年、わが国の大学において、教学マネジメントを支える「教学IRデータ分析」の基礎力と実務力を身につけた「教学IR人材」を育成することが急務になっています。
また、第4期機関別認証評価の最重要項目「内部質保証」においても、その実質化に向けて教学IRを活用した十分な調査・データの収集と分析が求められるようになってきています。
そこで、第7回講座では、その基礎力養成講座として、主に教学データの分析の具体的事例を用いながら、IR業務における問いを立てるプロセスを学ぶことを目的とします。
IRにおける問いとは、日常業務において出てくる疑問を解決するために立てるもので、大学のミッションやビジョン、目標に即して設定され、検討可能な形で表現される必要があります。
第1章では、初心者でもしっかりと理解できるように、教学IRの問いの立て方の基本をわかりやすく解説します。
第2章では、「奨学金」と「エンロールメント・マネジメント(EM)」を取り上げて、教学IRの分析事例を紹介します。
第3章では、「内部質保証の実質化」をテーマに、実際に問いを立てて、教学IRの活用に至るまでの一連の流れについて、個人ワークを通して学習します。
第1章 教学IRの問いの立て方―基本編-
- 本講座の目的と背景:「問い」を立てる重要性、業務における問いと教学IRの関係
- IRにおけるRQ(リサーチ・クエスチョン)とは
- RP(リサーチ・プロブレム)
- 問いの立て方:IRにおけるRQの要件、RQの構造化、IRにおける問いの事例
- 課題の整理方法の紹介
- 問いの立て方の基本の流れを説明(①課題の洗い出し(RPを書き出す)、②課題の整理、③問い(RQ)の設定、④分析)
第2章 教学IRの問いの立て方
―事例編「奨学金とEM」-
- 問いの立て方の事例/奨学金編:教学IR業務における奨学金の分析事例紹介
- 問いの立て方の事例/エンロールメント・マネジメント編:教学IR業務におけるエンロールメント・マネジメントの分析事例紹介
第3章 教学IRの問いの立て方
―個人ワーク編「内部質保証」-
- 個人ワークのテーマ「内部質保証の実質化に向けた教学IRの活用」
- 実際に問いを立て、教学IRの活用に至るまでの一連の流れを個人ワークを元に学ぶ
- 課題の洗い出し・整理・問いの設定
- 個人ワーク結果の発表と姉川先生からのフィードバック
- まとめ―RQの要件―
- 参考文献の紹介
「教学マネジメント指針」でも指摘されているとおり、わが国の大学には、①授業科目レベル、②学位プログラムレベル、③大学全体レベルの3つのレベルで、「学修成果の可視化」と「教学IRの機能強化」が求められています。
また、第4期機関別認証評価から、すべての機関別認証評価機関において、「学修成果の可視化」をより一層重視した評価が行われています。
さらに、「知の総和」答申では、IRを通じた自己点検・評価や認証評価での「全国学生調査」の結果を積極的に活用することが要請されています。
そこで、第8回講座では、「教学IRデータ分析」の実務力養成講座として、3つのレベルの「学修成果の可視化」と「教学IRの機能強化」に関するテーマを取り上げて、個人ワークを実施し、教学IRの実務力を身につけることを目的とします。
第4章では、教学マネジメント体制を支えるIRの役割について概説するとともに、いかに多くの課題の中から重要なものを選び出し、課題解決に向けて実質的なIRを行っていくかを説明します。
第5章から第7章では、「授業評価アンケート、卒業生調査、学修行動調査、全国学生調査」をテーマに取り上げ、3つのレベルの実際の分析事例を紹介しながら、個人ワークを行います。
3つのレベルに分けた「学修成果の可視化・教学IRの機能強化」の方法を体系的に学べるのは、ビズアップ総研の講座だけです。
他大学の受講者のワーク結果を学ぶことができるとともに、姉川先生からのフィードバックを通して知見を広められる貴重な機会となりますので、ぜひ、多数の方々からのご参加をお待ちしております。
第4章 教学マネジメントにおけるIRの役割
- 「教学マネジメント指針」の概説
- 教学マネジメント体制を支えるIRの役割の説明
- 多くの課題の中から重要なものを選び出すやり方
- 課題解決に向けて実質的なIRを行っていく方法
第5章 ①授業科目レベルの「学修成果の可視化・教学IRの機能強化」
- 個人ワークのテーマ「授業評価アンケート」
- 課題の洗い出し・整理・問いの設定
- 個人ワーク結果の発表と姉川先生からのフィードバック
- まとめと解説:全体のまとめと解説、実際の分析事例を紹介
第6章 ②学位プログラムレベルの「学修成果の可視化・教学IRの機能強化」
- 個人ワークのテーマ「卒業生調査」「学修行動調査」
- 課題の洗い出し・整理・問いの設定
- 個人ワーク結果の発表と姉川先生からのフィードバック
- まとめと解説:全体のまとめと解説、実際の分析事例を紹介
第7章 ③大学全体レベルの「学修成果の可視化・教学IRの機能強化」
- 個人ワークのテーマ「全国学生調査」
- 課題の洗い出し・整理・問いの設定
- 個人ワーク結果の発表と姉川先生からのフィードバック
- まとめと解説:全体のまとめと解説、実際の分析事例を紹介
※プログラムの内容は変更となる場合がございます
受講者からの声
\森先生と田中先生担当の講座/
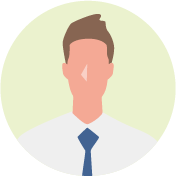
IRの初心者でしたが、森先生の講義で、IRに求められるものの全体像を把握することができ、とても勉強になりました。
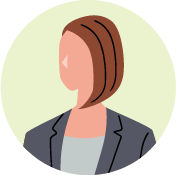
データ処理を学びたいと思い参加しました。田中先生の講座で、ExcelやAccessを使った演習があり、初歩から丁寧に教えていただき、基礎的な統計処理ができるようになりました。
\大石先生担当の講座/
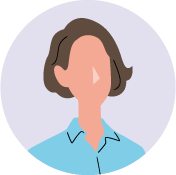
教育データに関する内容に興味がありました。
大石先生の講義で、他大学様が教育データを活用しどのような分析を行われているのかなどの事例紹介があり、たいへん参考になりました。
\今井先生担当の講座/

「大学DX」や「IRとDXの関係」を本格的に学べる講座がなかったので受講しました。今井先生の講座で、IRやDXの考え方を取り入れながら、業務改善や業務効率化を実現する方法を身につけることができました。
\姉川先生担当の講座/

姉川先生の教学IRにおける問いの立て方に関する講義は、現在の業務に直結しており、深い学びになりました。講義の中にあった事例をさっそく取り入れて運用していくところです。
\その他(講義資料、時間配分、後日配信の研修動画、修了証発行)/

各先生の講義資料がたいへん興味深く、また時間の配分も良く、充実した講座の内容で、参加した甲斐がありました。
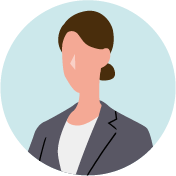
リアルタイムで参加できなかったので、後日の動画配信があるのが嬉しかったです。また、「すきま時間」を使ってその動画で復習ができて、とても便利でした。
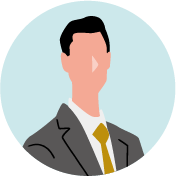
私立大学等改革総合支援事業を中心とする私学助成の配点区分に配慮した「修了証」を発行していただのが有難かったです。
|講|師|紹|介|

東京科学大学 戦略本部IR部門 教授
森 雅生 博士(情報科学)
IRを担う受講生の皆さまに、これまで私たちが得た経験や知識をお伝えし、
IRを導入する際の苦労が少しでも軽減できるようお手伝いしたいと思います。
1996年より九州大学助手、2006年より同大学 助教・准教授として大学評価・IRの研究と業務に従事、2015年より東京工業大学教授(IR専任)、2024年10月より現職。大学情報・機関調査研究会(MJIR)およびIRに関する学際的な国際学術会議DSIRを設立。2019年、日本インスティテューショナル・リサーチ協会(JAIR)を有志と設立し、会長・副会長・理事としてIRの普及活動を行う。2022年より会長。また、研究者IDであるORCIDの必要性に早くから注目、2020年にORCID日本コンソーシアムの設立を有志とともに行い、同コンソーシアム運営委員会の委員長としてORCIDの普及と展開に寄与している。

九州工業大学 教授
大石 哲也 博士(工学)
教育データの扱い方や諸技能を中心に、できるだけ具体的で
すぐに活用できるようにレクチャーいたします。
2004年より株式会社NTTデータ九州にてシステムエンジニア、2006年より九州大学システム情報科学府にて博士後期課程に進学し情報検索に関する研究で2010年博士 (工学)取得、2009年より同大学システム情報科学研究院に研究員等に従事、2013年より同大学 大学評価情報室にて助教として大学評価・IRの研究と業務に従事、2017年より東京工業大学にて情報活用IR室特任准教授、2022年より九州工業大学にて学習教育センターの教授に着任し、同年4月より同センターの副センター長に就任、現在に至る。2013年から大学情報・機関調査研究会(MJIR)に関わり、2018年から主幹幹事(2020年は委員長)として3年間MJIRを引率。2019年から日本インスティテューショナル・リサーチ協会(JAIR)の理事、2022年度からは同協会の評議員として、2024年度からは同協会の監事としてIRの普及活動へ貢献している。

北九州市立大学 経済学部経済学科 准教授
姉川 恭子 博士(経済学)
日頃から悩んでいることをどのようにIRとして分析まで繋げていくか、
具体的な事例を用いながら分かりやすく解説していきます。
早稲田大学助手(2014年ー)、助教(2017年ー)、講師(2018年ー)、東京工業大学特任准教授(2020年ー)を経て2022年4月より現職。早稲田大学大学総合研究センターでは、早稲田大学におけるIRを専門的に担う部署の立ち上げメンバーとして主に教学IRや大学評価、高等教育研究に携わる。東京工業大学では、財務データの分析にも従事。近年では科学研究費補助金を受け、学生のメンタルヘルス支援や、教養教育や学術会議に関わる高等教育研究にも精励する。主著に『大学IRスタンダード指標集』『大学総合研究センターの今』等。

東京科学大学 情報基盤センター マネジメント准教授
今井 匠太朗 博士(理学)
僕の担当講義は一見IRとは違う内容に見えますが、最後にIRと深く繋がります。
IRを通して大学改革を進める1つの実践的方法を解説します。
2013年大阪大学理学院物理学専攻にて博士号取得、以後ポスドクとして京都大学、北海道大学に所属。2015年9月より北海道大学特任助教、2020年1月より東京工業大学特任講師をへて2024年10月から現職。現職では大学経営改革およびDXの一環として業務改善の手法開発・実践および普及活動、デジタル化による情報の一元化をはじめとした学内情報流通の改善を推進している。

東京科学大学 戦略本部IR部門 室員
田中 要江
実務データに近い仮想データを用いて、データ処理や分析の実習を行います。
初心者を対象にしていますので、気軽に学んでいただければと思います。
2009年から、九州大学 大学評価情報室にて研究者情報のシステム管理およびデータのメンテナンスを担当。2011年から2013年まで、九州大学大学院 統合新領域学府 ライブラリーサイエンス専攻にて大学組織の意思決定に必要なデータの分析方法やデータの持ち方について学び研究を行う。2016年より東京工業大学情報活用IR室、2024年10月より現職、データ分析やシステム運用に従事する。
\8回おまとめ受講でセット割引あり/
受講料(税込/1名様あたり)
| 1講座あたり | 16,500円 |
| 第1回~第8回 すべて受講 | 8回受講セット割引特別価格 88,000円 |
※セット割引につきましては初回お申し込み時のみに限らせていただきます。
- 「大学IRプロフェッショナル養成講座」は全8講座となりますが、1講座のみのご参加も可能です。
- ただし、第1回と第2回、第3回と第4回、第5回と第6回、第7回と第8回は、それぞれ同じ講師による連続講義となっておりますので、両方の回を連続して受講していただくと、より一層学習効果が高まります。
- 本講座では、所定の課程を修了された方に「大学IRプロフェッショナル養成講座 修了証」を交付しております。「修了証」の交付をご希望の方は、お申込みフォームで、「修了証交付を希望」をお選びください。
- 社員教育の実施等を業とする同業者の方の参加は、ご遠慮いただいております。
- 同業者と思われる方のお申込みと認められた場合、ご参加をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 【 銀行振込でのお支払いをご希望の方 】
お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書」と「請求書」をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
※振込手数料は貴学又は貴殿にてご負担願います。
※お支払いの際に振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。 - 【 クレジットカードでのお支払いをご希望の方 】
お申込み受付後、「申込請書」ならびに、ご購入手続きの詳細をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
※「クレジットカード」での決済についてはStripeのシステムを利用しています。
受講方法
本講座は「Zoomによるオンライン研修」となります
インターネット環境とパソコン、マイク、スピーカー、WEBカメラがあれば
どこからでもセミナーにご参加いただけます!
- お申し込み後、ZoomミーティングID・PWを
開催日までにe-mail等にてお送りいたします。
(テキストは別途郵送等にてお送りする予定です) - 講義の録音・録画はご遠慮願います。
- Zoomのカメラ機能はオンの状態でのご参加をお願いいたします。

※ZoomおよびZoom(ロゴ)は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。