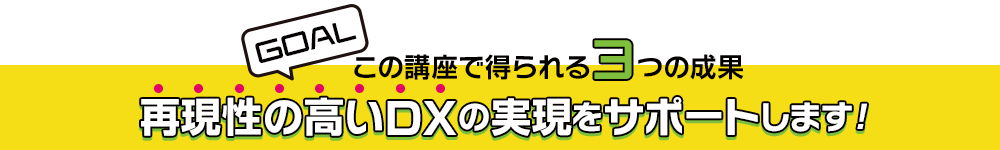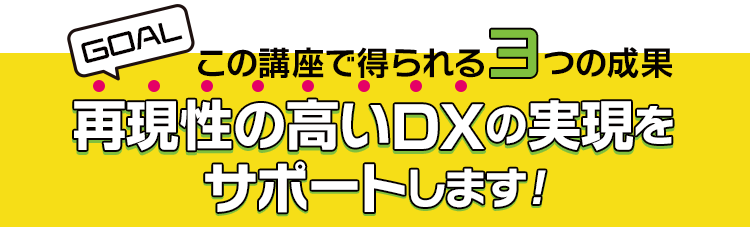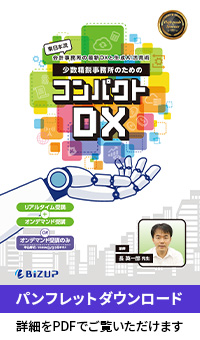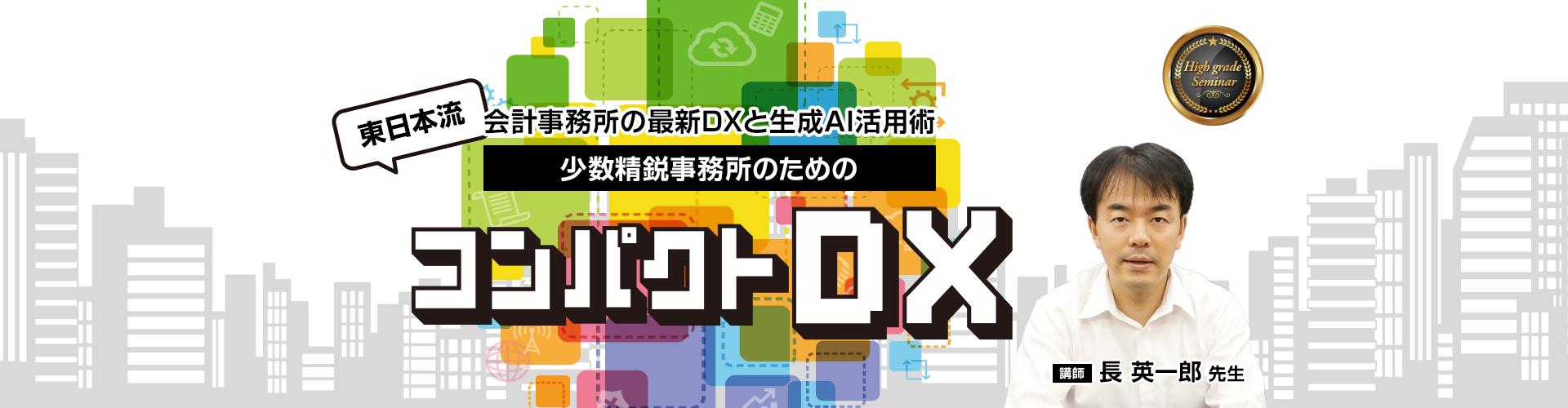
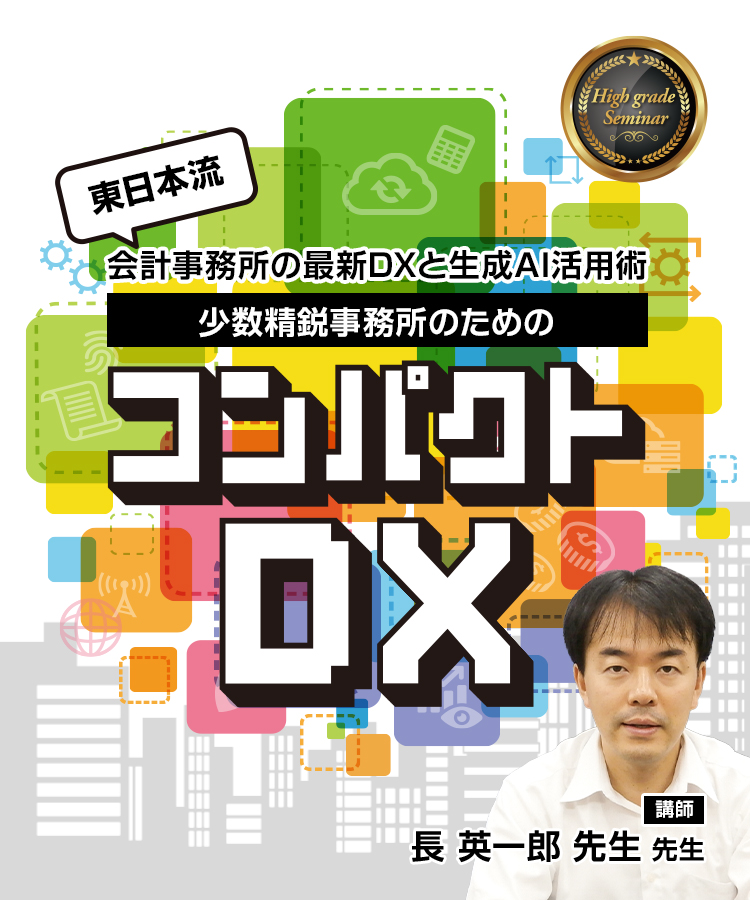
会計事務所の
DXは大きな事務所だけのものですか?
最近では、会計ソフトや業務管理ソフト、さまざまなSaaSやRPAを繋いで複雑な仕組みを作ることが、
会計業界でも“先進事例”として盛んに取り上げられています。
しかし、そのような手法は、所長先生がデジタルに明るく、しかも所内に元SEなどの人材がいることを前提に成立しており、
最大のボリュームゾーンである職員数5〜30名程度の少数精鋭事務所には馴染まないケースや、
実現が難しいケースがほとんどです。

盛んに紹介されているDX・AI活用の最新事例を見て、
このように感じることはありませんか?
● うちみたいな少数精鋭の事務所で、そこまで複雑な仕組みはいらないし、導入できないよ!
● DXは複雑すぎる。やっぱりDXは大きい事務所のものだ!
実はいま、このような声が
実際に全国の事務所から聞こえてきます。
この講座では、日本中の会計事務所の約8割以上を占める「職員30名以下」の事務所様が、
「大きなコストをかけず職員さんにも負担をかけないDX」
「職員さんにも“やってよかった”と思ってもらえるDX」の進め方を、
医業特化事務所として全国的にも有名な東日本税理士法人の取り組み事例を通じて体得していただけます。
| いわゆる『先進DX 事例』 |
|---|
| 複雑なSaaS 連携・RPA 導入 |
| DX 人材の専任が前提 |
| 大規模投資が必要 |
| 道半ばで力尽きることも |
| 東日本流『コンパクトDX』 |
|---|
| 少人数でも回るシンプル設計 |
| 職員全員が自然に活用できる |
| 小さく始めて効果を実感 |
| 再現性のある仕組み化 |
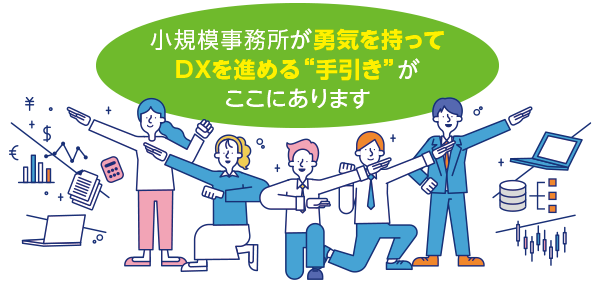
「小さく始めて成果を出す」
DXの具体像を理解できる
● 複雑なSaaS連携やRPA前提ではなく、少人数でも回るシンプル設計のDXを学べる。
● 大規模投資をせず、小さく始めても効果を実感できる実例を体得できる。
● 東日本税理士法人の具体的な改善事例を通じて自事務所に即した応用のヒントを持ち帰れる。
「9割の職員が日常的に使う」
生成AI活用法を習得できる
● ChatGPT・Claude・Geminiなど、主要な生成AIの強みと使い分けを理解できる。
● 導入初期につまずきがちな「誰も使わない」状態を乗り越える、浸透の仕組みを学ぶ。
● 会計事務所業務に直結するAI活用事例を具体的に持ち帰れる。
職員が
「やってよかった」と思える
DX・AI経営の進め方を掴める
● 残業削減・離職率低下・業務スピード向上など、経営と働き方改革の両立につながる仕組みを理解できる。
● DX・AIを“特定のDX人材”に依存せず、職員全員が自然に使える仕組み化の考え方を学べる。
● 自事務所に合ったペースで導入し、再現性を持って継続できるDX戦略を描けるようになる。
東日本税理士法人とは
医療、特に病院の税務・会計指導から経営コンサルティングまで、日本トップレベルの実力を誇る少数精鋭事務所。
働き方改革を機にDXに本格的に取り組み、コロナ禍の終焉から2年が過ぎた2025年現在でもリモートワーク率9割を誇る。代表の長英一郎先生は、さまざまなITツールやSaaSに精通しており、2023年にChatGPTが公開されて以降、業界内でどこよりも早く生成AIを全職員に導入。所内でChatGPTの「GPTs」やClaudeの「プロジェクト」といった“カスタムAI”を活用するだけでなく、医療の現場に特化した生成AIの導入も支援している。
◎ 従業員の生成AI利用率9割越え
◎ 20名規模の事務所で常勤事務職員はわずか1名
◎ 物価が高騰する中、販管費を数百万円単位で削減!
全国トップレベルの専門特化業務を
フルリモートで実現している
“仕組み”も公開!
プログラム
➊ 東日本税理士法人のDXの歩み
- DXへの取り組みの歴史
- DX化の過程で直面した課題&解決法
➋ 東日本税理士法人のDX事例を大公開!
- DX①:小口現金化ゼロ化の取り組み
- DX②:リモートワーク
- DX③:電話応対ゼロ化
➌ 日本一の専門性を支える「生成AI活用術」
- 東日本税理士法人の生成AI活用術「使用ツール&具体的活用シーン」
- 業務ごとにベストな生成AIを使い分ける
①ChatGPTが得意な会計事務所業務と
②Claudeが得意な会計事務所業務とは? - 生成AIを所内で一気に普及させた方法とは?
《第1章》
一斉退職から復活! 東日本流「DX経営」
➊ 失敗の連続だった「働き方改革」
- 20時強制退社で3人の税理士が退職
- 大量離職を機に経営理念の変更
➋ コロナを機にDXを推進 東日本の改革事例
- 2020年4月から今まで続く完全在宅勤務体制
- 在宅勤務の壁になった電話・FAX・郵便
- 時々会うことで人間関係での離職が減る
- 脱Excelにより属人化の解消
- 最後の砦となった勤怠DX
➌ DX化の事例
- 代表電話が鳴らないAI電話
- FAXの新着はチャットに通知
- マネーフォワード会計を軸にしたバックオフィス改革
- サイボウズからChatwork +Googleドライブへの引越し
- 顧客も喜ぶクラウド契約、クラウド請求
- 経費精算→勤怠→給与計算→会計を一気通貫に
- 小口現金ゼロにより現金不正リスクを減らす
- 経営会議はYouTube動画で事前配信
《第2章》
職員の9割が生成AIを活用するまでの道筋と最新活用術
➊ はじめての生成AI
- 生成AI御三家(ChatGPT、Claude、Gemini)
- プロンプト(命令文)、事前学習項目の使い方
- 委託費など費用削減とともに売上も向上
➋ 誰も使ってくれない生成AI
- 嘘ばかりつくChatGPT
- 有名YouTuberを招いて研修会を実施するも、
新人しか使ってくれない生成AI
➌ 利用割合9割までの軌跡
- あえてはじめから有料版を使う
- 月1回の生成AI活用事例発表会
- 質問対応でどう使う? ChatGPT
- 生成AIの回答精度を上げるための工夫
- 生成AIからプログラミングなど次のステージへ
➍ 生成AI活用事例
- Claudeによる財務諸表分析
- Claudeによる文章作成
- Gammaによるプレゼン資料作成
- NotebookLMによる社内資料Bot
- ChatGPTディープリサーチによる顧客質問対応
- Geminiによる動画マニュアル作成
- Geminiによるスケジュール登録
※プログラム内容が一部変更になる場合がございます。
受講料(税込/1名様)
| 第1回 | ★受講料無料 |
| 第2回 | 55,000円 |
- 【 銀行振込でのお支払いをご希望の方 】
お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書」と「請求書」をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、受講料のお支払いをお願いいたします。
※振込手数料は貴社にてご負担願います。
※お支払いの際に振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。 - 【 クレジットカードでのお支払いをご希望の方 】
お申込み受付後、「申込請書」ならびに、ご購入手続きの詳細をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、受講料のお支払いをお願いいたします。
※「クレジットカード」での決済についてはStripeのシステムを利用しています。
|講|師|紹|介|

東日本税理士法人 代表社員
公認会計士・税理士
長 英一郎 氏
公認会計士・税理士としての専門性に加え、ACLS(高度心肺蘇生法)プロバイダーの資格も保有し、「患者視点の医療経営」をモットーに活動している。
医療・介護現場のリアルを知るため、病院や施設の体験見学を重視しており、国内にとどまらず海外にも積極的に足を運ぶ。その体験から得た知見は、講演やSNSを通じて広く発信している。近年ではChatGPTなどのAIツールも積極的に取り入れ、医療・介護の現場における新たな情報発信と業務効率化にも取り組んでいる。